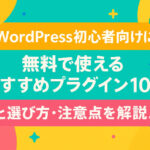ブログは、継続できるかどうかがすべてと言っても過言ではありません。
始めたばかりの頃は意欲に満ちていても、1週間、2週間と経つうちに書くことが億劫になり、やがて更新が止まってしまう人が非常に多いのが現実です。
- ネタが思いつかない
- 誰にも読まれない
- 毎回ゼロから考えるのがつらい
こうした悩みは、多くの初心者ブロガーや副業ライターが直面する共通の壁ですが、ブログを続けている人たちは、決して根性などの精神論で乗り越えているわけではありません。
継続するしくみと企画を持ってさえいれば、苦痛なく更新を続けられます。
本記事では、ブログを継続できない理由と、それを乗り越えるための具体的な習慣化テクニックを紹介します。
精神論ではなく、心理学や行動デザインにもとづいた続けるための実践術を知ることで、ブログ運営スタイルが大きく変わるはずです。
なぜブログを続けられないのか?失敗する人の共通点
ブログを始めた人の90%以上が、3ヶ月以内に更新を止めると言われていますが、もっと早いかもしれませんね。
「何を書けばいいかわからない」「時間がない」「書くのが苦痛」など理由はさまざまですが、背景にはいくつかの共通点があります。
目的があいまいなまま始めている
「副業になるらしい」「稼げるって聞いた」といった動機で始めても、成果が出るまでには時間がかかります。
すると、こんなに頑張っても誰にも読まれないという現実に直面し、やる気が低下して徒労感に苛まれるのです。
誰のために、何の目的で書いているかが明確でないと、継続のモチベーションが持ちません。
本当の動機に立ち返ることが、習慣を取り戻すきっかけになります。
1記事に完璧を求めすぎて時間がかかる
非常によくあるパターンですが、「ちゃんと書かなきゃ」「恥ずかしくないように」と真面目過ぎるあまりに悩み、脱線し、何時間もかけて結局、下書き止まり・・・。
恥ずかしい話ですが、私も経験あります。
いわゆる完璧主義の罠にハマると、書くこと自体がストレスになっていきます。
理想が高いこと自体は悪くありませんが、それが公開できない言い訳になってしまっては本末転倒です。
まずは「5割~7割の仕上がりで投稿OK」と、自分に許可を出し、更新によって満足度を満たす考え方がおすすめです。
ただし満足度に関しては、自分へ向けるのではなく、あくまでも読み手に対するものとしてくださいね。
ネタ探しが作業になっていて楽しくない
ネタ切れの最大の原因は、日常にアンテナが立っていないことです。
普段の体験や気づきをネタ候補として意識する習慣が無ければ、毎回、GoogleやSNSで「ブログ ネタ」での検索やトレンドに振り回されるだけになります。
単なる日記ならば「これ書きたい!」というスタンスで構いませんが、副業や副収入の手段とするならば、ニーズの有無や経験の棚卸が求められます。
読まれないことで無価値を感じてしまう
せっかく時間をかけて書いたのに、アクセスがゼロ、コメントもゼロ、反応がまったくない・・・。
このとき感じてしまう「自分の文章は意味がないのでは?」という感情は、ブログ継続における最大の敵です。
読まれない=価値がない、と捉えてしまう、続ける理由が見えなくなってしまうためです。
ところが実際には、読まれていないことと価値がないことは、イコールではありません。
ほんの少し、企画やテーマとニーズのズレを改善し、SEOという根本的な技術について学べば、化ける可能性は十分にあります。
続けるしくみが存在していない
結局のところ、多くの人が挫折する最大の理由は、継続のしくみがないことです。
たとえば、「毎日21時にパソコンを開く」「まずリード文だけ書く」「ネタメモは朝の通勤中に書く」など、自分なりの継続の型がある人ほど、楽に続けられています。
続けられる人と続かない人の違いは、才能ではなく行動にスイッチを入れるトリガーを生活に埋め込んでいるかどうかに過ぎません。
日常のルーティーンや習慣の中に、小さなトリガーを埋め込めば、継続につながっていきます。
ブログを続けるための7つの習慣化テクニック
ブログを継続するために必要なのは、精神的な支えではなく、習慣化といえます。
ここでは、今日から実践できる7つの具体的なテクニックを紹介します。
どれも特別な準備や才能を必要としない、再現性の高い方法ばかりです。
① 書くハードルを徹底的に下げる
100点の記事を書こうとすると、手が止まってしまいます。
まずは「メモレベルでもいい」「とりあえず公開する」と割り切って、完璧を目指さないスタンスを持つことが大切です。
見出しやリード文だけ書いて下書き保存など、一歩だけ進める癖が続ける力になります。
② ネタ帳を持つ|思いつきをメモで逃さない
ネタ切れは、何か思いついたりヒントを得たりしたとしても、自ら勝手に却下する思考も原因のひとつ。
または、忘れるという、シンプルなものもあります。
ブログに書けそうと思った瞬間を逃さないよう、常にメモをする姿勢、状態にしておきましょう。
Google Keep、LINEのひとりグループ、Notionなど使いやすいツールでOKです。
テーマ候補をストックしておくことで、何を書こうか悩む時間が減り、組み合せや発想・着想のきっかけにもなります。
③ 型(テンプレ)で書く癖をつける
毎回、構成をゼロから考えていると、時間も気力も消耗します。
PREP法(結論→理由→具体例→まとめ)やQ&A形式(質問→答え→根拠)など、基本的な構成パターンを使いましょう。
文章の型を身につけることで、書くスピードが格段に上がり、迷いが減ります。
④ 書く時間帯と場所を固定する
いつでも、どこでも書けることが理想ですが、それは、しくみが確立して習慣が身についている場合のみ。
生活スタイルに合わせて、ブログ時間を組み込んでみましょう。
場所も重要で、デスクに座ったらブログを書くという環境を整えるだけで、脳が自動的に執筆モードになることもあります。
パソコンやスマホに、執筆途中の画面を表示しておくこともおすすめです。
スイッチが入る時もありますから。
⑤ インプット→アウトプットをセットにする
本を読んだ、ニュースを見た、人と話したといった日常のインプットを、すぐにブログでアウトプットする習慣を持ちましょう。
内容を忘れないうちに文章化することで、記憶にも残りやすく、ネタも自然と増えていきます。
レビュー・要約・感想など、自分の視点を添えるだけでオリジナルコンテンツになります。
これが専門特化したブログの運営にも、通じるものがあります。
⑥ SNSで宣言&共有して習慣の可視化
「今日は1記事書きます!」「今朝も更新完了しました」とX(旧Twitter)などで宣言するだけでも、行動へのブレーキが減ります。
毎日じゃなくてもOK。
週1でも「言ったからやる」を繰り返せば、自然と投稿習慣が身につきます。
読者の反応やフィードバックが得られなくても、習慣化が目的なのであまり気にせずに。
⑦ 人に伝える意識を持つ
「誰か1人でもこの情報を知って楽になってくれたら」
このマインドがあると、書くモチベーションは下がりにくくなります。
特に専門的な内容をブログに投稿するのならば、最も大事な視点です。
日記・コラムだとしても、読者のちょっとした悩みや不満・課題などの解決を意識した文章を添えるだけで、アクセス数も継続意欲も上がっていくことがあります。
それでも書けない時の対処法
どれだけ工夫しても、今日は本当に書けないという日、しょっちゅうありますよ。
納期やスケジュールの都合で、なんとしてでも仕上げなければならないとき以外は、思い切って何もしないのもひとつの手段です。
無理して続けようとすると、ブログ自体が嫌いになるどころか、ヒドイ文章になってるんですよね。
とはいえ、せっかくなので書けないと感じたときの具体的な対処法を紹介しますが、前提としては、書けない自分を責めずにしくみで回避です。
① 書かないことに罪悪感を持たない
「毎日更新しなきゃ」「1日でも休んだら終わり」と思い込んでいたら、即刻、改めましょう。
これが業務命令だと仕方がありませんが、自由の利くフリーランスや隙間時間での副業ならば、追い詰めなくてもよいのでは?
継続の秘訣は、途中でやめても、また戻れる柔軟さにあるからです。
休んだとしても、書く価値が下がるわけではありません。
② 1行だけ書いて終えてもいい
何千文字の記事を書こうと意気込むと大きなタスクに感じますが、1行だけでいい日を設けると楽になります。
リード文1行、見出し1個、結論のひとことだけ…。
もしくはXで一行つぶやくとか。
内容はともかく、それだけで書いた事実は積み重なりますからね。
不思議と1行書くと、もう1行書きたくなったりすると、その流れに乗ればOK。
書くことへの心理的ハードルを、自ら下げてしまえば、再開の第一歩も踏み出しやすいものです。
③ 過去記事をリライトする
新しい記事が書けないときは、過去の記事を読み返して、リライトしてみてください。
誤字脱字を直すだけでも、ブログに触れている状態になりますし、訂正や修正箇所を見つけると、書く力が付いてきてるかもと実感できます。
追記や構成の調整をしていくうちに、「あ、この内容もう少し掘り下げて書きたい」と意欲が湧いてくることもあります。
ゼロから書かなくても、改善や補足も立派なブログ運営の作業です。
④ 書かなくてもブログ活動はできる
ネタの整理、構成の下書き、画像の選定、リンクの見直しなど、執筆以外にもできることはたくさんあります。
記事そのものを書かなくても、次に書く準備をする時間は無駄になりません。
ある記事の派生したテーマを書きたい、この記事はシリーズ化して別媒体で公開できそうだといった、構想を練ることも必要なんです。
収益を得たいならばね。
1人1ブログと決まってるわけではないので、自由に広げて楽しみを増やすことも重要です。
⑤ あえて非公開で書いてみる
書きたいけど、読まれるのは少し恥ずかしい、なんて奥ゆかしい人もいます。
そんな時は、非公開または限定公開なんて、いかがでしょうか。
私は仕事なんで、公開しないつもりで書くことはありませんが、下書きも非公開の一部と考えると、不思議なほど筆が進むことが正直あります。
人目を気にしないという心構えも、捨てたものではないのかもと考えてます。
誰かに読ませる文章をいったん手放すと、本来の自分らしい表現がスッと出て、実はめちゃくちゃ読みやすい、わかりやすいってことゼロではありません。
⑥ 書けない原因を紙に書き出す
なぜ書けないのかが自分でもわからない場合は、その気持ちをそのまま紙に書いてみましょう。
「書く気が出ない」「何から始めていいかわからない」と言葉にすることで、もやもやが明確になります。
可視化するだけで、不安や停滞感は半減します。
ところが書けない気持ちを書いて公開すると、意外に読んでくれることって、あるんですよ。
その書けない悩み、実は多いですから、ストレートに表現すると共感してくれる人は多いので、決して無駄な執筆にはなりません。
⑦ ブログから少し距離を置く
一番大切なのは、無理に続けなきゃと思わない!
※ただし仕事として請け負った分は別
比較的自由に書いてる自身のメディア(オウンドメディア)なら、2〜3日、思いきって管理画面にログインすらせず、気持ちをリセットするのも有効です。
その間に、読者として他人のブログを読んだり、まったく別の体験をすることで、新たなネタや視点が生まれることもあります。
間違っても迷惑系動画を投稿するような、ちょっとワケアリな記事を書きなぐって公開するするなんぞは、絶対にしないようにしましょうね。
そんな記事が目に留まって、スカウトとかチャンスを逃すかもしれない。
まとめ
ブログを継続するには、「やる気」や「才能」よりも、しくみと習慣化の工夫が何より大切です。
多くの人が挫折する原因は、書くハードルの上げ過ぎ、理想と現実のギャップに苦しむ、といった点にあります。
その壁は、ちょっとした考え方の転換や、環境次第で乗り越えられることがほとんど。
まず1行、もしくは1つメモ、そんな小さな行動の積み重ねが、きっかけになります。
書けない時は、(スケジュール次第ですけど)休憩・休息を選択しても大抵は大丈夫。
プロ野球の選手でも、ヒットが出ない日もありますし。
一休みした後、また、書き続けられれば継続の証となります。
もし、行き詰ったときは、この記事で紹介したテクニックが少しでも参考になればうれしいです。